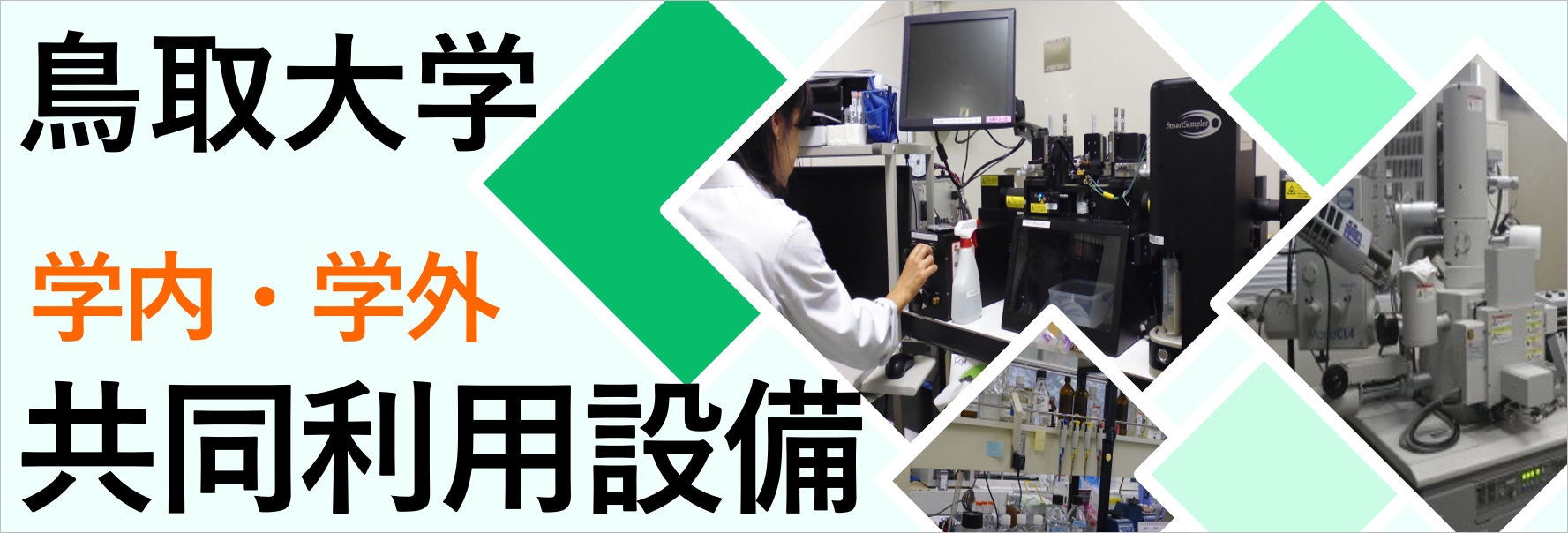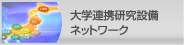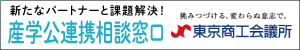- ホーム
- 研究基盤センター
- 学内の方向け
- 各種マニュアル(技術・情報提供)
- 遺伝子応用技術コース(細胞への遺伝子導入とその発現実験)
遺伝子応用技術コース(細胞への遺伝子導入とその発現実験)
目次
1. 発現ベクターの構築
ある遺伝子の機能を探る場合、選択肢としては、1) 培養細胞系への遺伝子の一過的(transient)または安定的(stable) 発現による機能解析、2) アンチセンスオリゴヌクレオチドやsiRNAなどを用いた遺伝子の発現抑制による機能解析、3) 遺伝子改変動物作成による機能解析、4) 動物への一時的遺伝子導入、発現による解析などの系が考えられる。ここでは、培養細胞への遺伝子発現の系を目的とした発現ベクターの構築について学ぶ。
発現ベクターのデザイン
目的遺伝子のcDNAが入手、またはPCR法で増幅できたならは、その遺伝子を細胞に発現させてどんなことが起こるかを検討することができる。そこで発現ベクターを選択する必要がある。そのためにはまず対象となる細胞を決め、あとは選択マーカーを考慮したうえで目的の細胞にあったベクターを入手する。今回はEGFP-tagging発現ベクター(pEGFP-C1)を用いる。
プロモーターの選択
- 幅広い細胞種を標的にする場合のプロモーター
- 細胞・組織特異的プロモーター
- 発現調節ベクター
- 選択マーカー遺伝子の選択
CMV、SV40、TKなど。
TetやCre-lozPシステムなど。
neo、hygr、bsdなど。
2. GFP法
蛋白質の生物学的な役割を知るうえで、個体もしくは細胞レベルでの蛋白質の曲在を分析することは重要である。従来の蛍光抗体法では、細胞を固定した状態で観察することになり、時間を追った曲在分布を生きた個体、または細胞内で観察することは不可能である。GFP(green fluprescent protein)はクラゲの一種、Aequorea Victoriaから分離された蛋白質で、個体および細胞内での蛋白質の曲在研究もしくは、遺伝子発現および蛋白質間の結合等のレポーター分子をして応用される。EGFP(enhanced GFP)はGFPの変異体で、より安定で強い蛍光を発し、実験が容易になった。さらにCFP(cyan fluorescent protein)やYFP(yellow fluorescent protein)などの変異体やDsRed(Discosoma sp. Red fluorescent protein)などの他の生物から分離された蛍光蛋白質も開発されている。本講習会ではGFP発現ベクターpEGFP-C1を用い、目的遺伝子産物を融合させる方法を学ぶ。
メモ
発現させる蛋白質によっては、N末端もしくはC末端と結合すると、本来の蛋白質の動態が疎外される場合がある。抗体が入手可能な場合は、通常の蛍光抗体法と比較する必要がある。それが不可能な場合は、CおよびN末端に結合させた蛋白質を作製し、比較することができる。また、融合蛋白質の機能解析が可能な場合は、GFPの有無で機能に変化がないことを示すことも必要となる。GFPと目的蛋白質の間にスペーサーを入れると良い場合もある。
方法の概略
- GFP融合発現ベクター構築のためのPCRプライマーのデザイン
- PCR法による全長cDNAの増幅
- クローニングベクターへのサブクローニング
- 制限酵素処理によるcDNAの切り出しとベクターの切断
- GFP発現ベクターへのcDNAのクローニング
PCR法による全長cDNAの増幅
| template DNA (ATP7a cDNA) | 1 ul |
| 10x PCR buffer | 2 ul |
| MgCl2 | 1.6 ul |
| dNTPs | 1.6 ul |
| primer mix | 4 ul |
| Taq DNA polymerase | 0.1 ul |
| dH2O | 9.7 ul |
| total | 20 ul |
| サーマルサイクラーの条件 | ||
| 95℃ | 5min | x1 cycle |
| 95℃ | 30sec | x30 cycles |
| 58℃ | 30sec | |
| 72℃ | 4min | |
| 72℃ | 5min | |
制限酵素処理によるPCR産物とGFP発現ベクターの切断とライゲーション
- 1%アガロースゲル電気泳動で目的のPCR産物 (4.5 kb)を確認する。
- QIA quick PCR purification kit (QIAGEN)を用い、PCR産物をゲルから精製する。
- 精製したPCR産物とGFP発現ベクターpEGFP-C1を制限酵素処理により切断する。
- アガロースゲル電気泳動とQIA quick PCR purification kitにより、切断PCR産物とGFP発現ベクターを精製する。
- ライゲーション
- 室温3-5時間、または16℃一晩インキュベーションする。
| PCR product | 1 ul |
| GFP発現ベクターDNA | 1 ul |
| 10x T4 DNA ligase | 1 ul |
| T4 DNA ligase | 1 ul |
| dH2O | 6 ul |
| total | 10 ul |
トランスフォーメーション
準備
- コンピテントセル: JM109
- SOC medium
- LB broth
- LB plate
- Falcon 2059 tube
- Antibiotics : アンピシリン or カナマイシン
- Water bath : 42℃と37℃
方法
- コンピテントセルを氷中で溶かし、解けた時点でFalcon2059チューブに移す。
- plasmid DNAを2 ul加え静かにピペッティングする。
- 氷中で10分間置く。
- 42℃ 45秒間、ヒートショックをかける。
- すぐに氷中に移す。
- SOC mediumを1 ml加え、37℃ 1時間でインキュベーションする(125 rpm)。
- カナマイシン含有(最終濃度30ug/ml) LB plateに捲き、37℃で12-16時間培養する。









プラスミドDNAの確認とlarge prep
- トランスフォーメーション後、出て来たコロニーを2-5mlのカナマイシン含有LB medumに移しさらに37℃で培養する。
- プラスミドDNA mini prepで精製したDNAを制限酵素切断とDNAシークエンシングにより確認する(特にGFPとの融合部位は必ず確認が必要)。
- プラスミドDNAを確認後、目的の細胞への導入法に従い、再度プラスミドDNAの精製(large prep.)を行い、トランスフェクション用のDNAを調整する。例えば、Maxi or midi prep. (Quiagen、Promegaなど)、または塩化セシウム超遠心法などがある。
3. リポフェクション法
リポフェクション法は細胞への遺伝子導入法のひとつであるが、脂質小胞(リポソーム)と導入するDNAとの複合体を形成させ、貪食や膜融合により細胞に取り込ませる方法である。必ずしもリポソーム内にDNAを封入しない点で、リポソーム法とは区別される。他の遺伝子導入法として、リン酸カルシウム共沈法、DEAR-デキストラン法、エレクトロポレーション法、マイクロインジェクション法、またはウイルスベクターを介した導入法などがあるが、以下の長所と短所がある。
- 長所
- トランスフェクション効率が比較的高い
- プラスミドDNAだけでなく、オリゴヌクレオチド、mRNA、二本鎖RNAの導入が可能
- 操作が簡便で要する時間も短いので、同時に多数のサンプル処理が可能。また、特別な装置・準備を必要としない。
- 他の方法と比べて細胞に対する毒性が少ないため、トランスフェクション後の細胞生存率が高く、一過性発現にも安定型発現にも用いることができる。
- 幅広い細胞に適応が可能(浮遊、付着を問わない)。
- 短所
- 至適条件(細胞密度、DNA/リポソーム量、培養時間など)の検討が必要。
- 一般に、試薬が高価である。
現在、リポフェクション試薬は各社各種販売されており、各自の細胞や用途に適したものを選択できる。LipofectinTM, Lipofect AMINETM , Lipofectamine 2000 (Invitrogen) FuGENE6 (Rocche) など。
方法の概略(参考)
- 付着細胞へのリポフェクション法
- COS-7細胞への一過性発現
- 細胞を捲いて一晩培養
- DNA/リポフェクション試薬の混合液を培地に混ぜ速やかに細胞にかける
- CO2培養器で3~5時間培養
- 新鮮な10%血清添加培地を加える
- 1-3日間培養
- アッセイ
- CHO細胞への安定型発現
- 細胞を捲いて一晩培養
- DNA/リポフェクション試薬の混合液を培地に混ぜ速やかに細胞にかける
- CO2培養器で3~5時間培養
- 新鮮な10%血清添加培地を加える
- 1-2間培養
- 細胞をはがし、薬剤含有培地に培地交換
- 1-2週間選択培養(要培地交換)
- 薬剤耐性クローンを得る
- アッセイ
- 浮遊細胞へのリポフェクション法
- 培養皿に培地と至適濃度のトランスフェクション試薬を加える
- 至適量のDNAを加える
- 細胞密度を調整し培養皿に加える
- CO2培養器で3-5時間培養
- 新鮮な10%血清添加培地を加える
- 1~3日間培養
- アッセイ
FuGENE 6 Transfection Reagenetを用いたCOS-7細胞への一過的発現
準備
- 細胞:COS-7細胞
- 血清添加培地:10%FCSを含むDMEM培地
- 無血清MEM培地
- プラスミドDNA:pEGFP-N1, pDsRed2-N1など
- 5mlポリエチレンラウンドチューブ:FALCON(2058)
- トランスフェクション試薬:FuGENE 6 Transfection Reagenet(Roche)

実験操作
- トランスフェクション前日、COS-7細胞を35mm>ディッシュ(カバーガラスが入っている)に捲く(メモ1)。
- 12mlチューブを2本用意し、100 ulの無血清MEM培地を入れる。(DNA溶液用と試薬液用)
- 試薬液用チューブに3ulのFuGENE6 reagentを加え軽くピペッティングで混ぜた後、室温で5分間置く。
- DDWに溶解した1ug分のプラスミドDNAをDNA用チューブに加え、ピペッティングする。
- DNA用チューブの溶液全量を、試薬液用チューブに加え、室温で15分間置きDNA/FuGENE6複合体を作らせる(メモ2)。
- 血清添加培地900 ulを加えピペッティング後、静かに細胞に添加する。
- CO2培養器で3時間培養(メモ3)。
- 3時間後、培地を除き新鮮な血清2mlを静かに加え、1晩培養する。








メモ
- 細胞の密度はトランスフェクション時に40~50%コンフルエントである。適正な細胞密度は細胞の種類や培地、増殖速度による。
- DNA/FuGENE6の量比は1:3である。その他、他の細胞や条件では2:3~1:6まで至適条件を決める必要がある。
- トランスフェクション後のインキュベーション時間も検討の必要がある。COS-7細胞の場合、3~5時間が至適時間である。
- 培養時間の検討も必要。COS-7細胞の場合、1日後から発現し始めだいたい3日目まで高い発現を示す。
4. 蛍光試料の調整と共焦点レーザースキャン顕微鏡による観察
医学、生物学の発展に蛍光顕微鏡が果たしてきた役割は大きく、培養細胞や組織内の物質の局在を知ることは、例えばプロテオミクスにおける蛋白質機能解析や、脂質のダイナミックな動態を観察するなど、今後もその役割はますます重要なものとなると思われる。
共焦点レーザースキャン顕微鏡(Confocal Laser Scan Microscope; CLSM)は蛍光顕微鏡の延長線上にあるが、その機能は大幅に強化されてきている。以下、CLSMが持つ特徴を列記する。
- Z軸上の分解能がきわめて高い
- 高画質である
- 多重蛍光染色試料での利点
- 機能解析機能(カルシウムイオン濃度の測定など)
- デジタル画像のため、取り扱いが容易
- コンピューター制御
蛍光試料の調整
準備
- PBS(-)
- 4% パラホルムアルデヒド溶液(pH 7.5)
- スライドガラス
- ゲルマウント剤(Biomeda): 蛍光退色防止剤
実験操作
- トランスフェクション後24時間のCOS-7細胞の培地を吸引後、PBS(-) 1mlで静かに2回洗う。
- 4% パラホルムアルデヒド溶液を1ml加え、アルミホイルで遮光し、室温で15分間細胞を固定する(メモ1)。
- PBS(-) 1mlで静かに2回洗う。
- スライドガラス上にゲルマウント剤を1滴落とし、その上に培養皿の中のカバーガラスを静かにのせる(メモ2)。
メモ
- 細胞固定液は細胞、検出する物質により最適なものを用いる。また蛍光抗体染色を行う場合は固定の後、抗原抗体反応を行う。
- このとき、スライドガラスとカバーガラスの間にできるだけ気泡をいれないよう注意する。
共焦点レーザースキャン顕微鏡による観察
実験操作
- レーザーのスイッチを入れ、15分以上ウォームアップする。
- スライドガラスをステージにセットする。
- 双眼鏡筒で試料を観察する。低倍の対物レンズからスタートし、最終的にレーザーモードで観察する対物レンズで、観察部位、焦点の確認をする。
- 顕微鏡をCLSMによる観察に切り替える。
- CLSMを蛍光色素に従ったセッティングにする。
- レーザーをスキャンさせ、共焦点画像をイメージモニター上につくる。
- 共焦点画像を最適化する。アベレージ画像をとるなど。
- 画像を保存する。