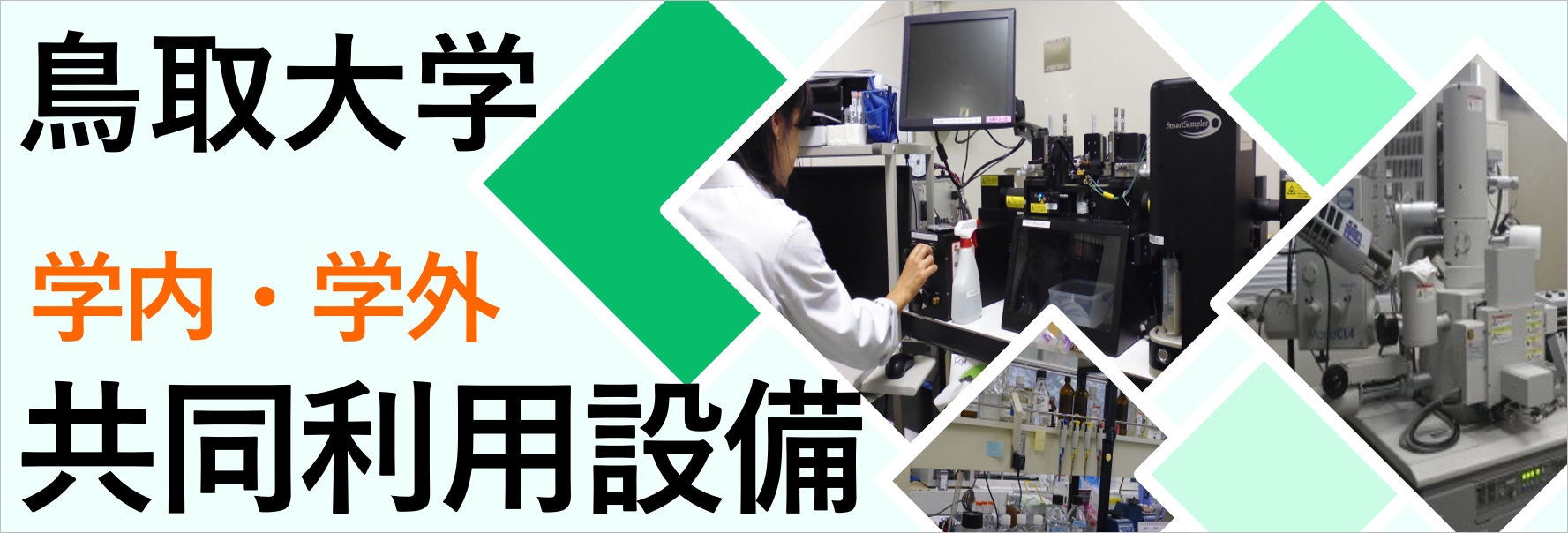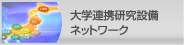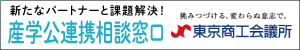- ホーム
- 研究基盤センター
- 学内の方向け
- 各種マニュアル(技術・情報提供)
- 準備・基本的な操作
準備・基本的な操作
目次
A. 器具の用意
遺伝子操作で用いる実験器具は無菌的であると同時に、DNase(DNA分解酵素)やRNase(RNA分解酵素)汚染されていないことが重要である。そのために、オートクレーブや乾熱滅菌できるものがよく用いられる。今回の実習では、頻回に用いられるピペットチップやサンプルカップのオートクレーブ滅菌を行う。
- ピペットチップ
あらかじめ、箱につめられているものはそのままオートクレーブにかける。また、箱詰めを自分で行う場合には、手袋をはめて操作を行い、皮膚についている雑菌やDNase、RNaseをつけないようにする。
- サンプルカップ
同様に手袋をはめ操作する。入れ物はインスタントコーヒーの空きビンなども良い。

- オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)の使い方
通常の機器は、水道水を適正な量入れ120℃、15分から30分程度のプログラムで滅菌する。この時に機器に入れてある水が汚れていないか確認すると良い。圧力が十分に下がった時点で、蓋をあける。器具は濡れているので乾燥機で乾燥させてから使用する。器具の滅菌の場合は、急速に減圧しても問題ないが、水溶液を一緒にいれている時は、絶対に急速に減圧しないこと。水溶液がビンから突沸する。
- RNAを扱う場合
RNaseは、オートクレーブ滅菌でも完全には失活せず、フェノール処理でも完全に除去できない。新品のプラスチック用品は、一般的にRNaseに汚染されていないので、オートクレーブ処理後に用いる。この時にオートクレーブ内が汚染されていないかどうか確認しておく。また、ガラス器具は240℃以上で2時間以上(または180℃で8時間以上)乾熱滅菌をかける。また、0.1%Diethy Pyrocarbonate(DEPC)を含んだ37℃の蒸留水(ミリQ水)に2時間以上つけて、その後オートクレーブをかけるのも有効である。プラスミド等を分離する時に大量のRNaseを用いる場合が多いので、実験室、ピペットマン、遠心機などの道具はRNA専用にするほうが望ましい。また、ピペットマン、遠心機などは掃除を丹念に行うのも効果的である。実験を行う時には手袋を着用したり、安全キャビネット等を利用したりして、RNaseの混入をさけることが望ましい。
B. 試薬の作成
高価ではあるが、すでに調製ずみの試薬も市販されている。代表的な試薬の具体的な作成方法は以下である。
- Tris buffer
Tris(hydroxymethyl)aminomethane (Tris bas) を12.1gビーカーにとりミリQ水(蒸留水)を加えて、約80mlにする。試薬をはかりとる時は、できるだけ薬匙等を使用しないのが良い。試薬瓶から直接から直接ビーカーに移す。最初はやりにくいかも知れないが、慣れると容易になる。スターラーバーを入れ撹拌・溶解する。pHを調整するためにconcHClを入れる。concHClは吸い込んだり目や皮膚に付着すると非常に危険なので、手袋をはめ、ドラフト等の下でピペッターエイドを用いて操作を行うのが望ましい。このバッファーはHClをいれると温度が上昇する。室温になった時のpHを8.0にあわせるようにする。時間をかけて行う方が良い。pHがそろったら、メスシリンダーに移し、さらにビーカーを少量のミリQ水で1-2回あらい、その溶液もメスシリンダーに移して一緒にする。ミリQ水をメスシリンダー内に加えて100mlに調整する。この溶液をまぜてから、試薬ビンに移しオートクレーブ(120℃、15-20分)処理をして室温で保存する。
- フェノール
 |  |
| 黄層がフェノール | 4℃で遮光保存 |
フェノールは上質なもの(molecular biology grade、生化学grade等)を用いるのが望ましい。上質でない場合は、再蒸留が必要な時がある。通常は白色の固体である。恒温槽に水を入れ、フェノールを瓶ごといれてから65℃にあたためる。65℃の水浴に、いきなり冷たいフェノール瓶を入れると割れることがあるので注意する。溶解したら、必要量を褐色瓶にとる。100mlのフェノールに0.1gの割合で8-hydroxy-quinolineを加え瓶を振って撹拌する。1M Tris-HCl(pH8.0)を等量加えてよく混ぜる。この状態で保存が可能である。使用する前に必要量をとり、等量の0.1M Tris-HCl(pH8.0)を入れ良くまぜ、遠心するか、静置して透明なTris bufferの層と黄色のフェノール層を分離させ、上層を捨てる。これを1-2回繰り返して、1cm程水層を残し、上層を捨てる。4℃で遮光保存する。色が赤みを帯びてくると使えない。
- TBE(5x)
電気泳動のバッファーのひとつである。
- Tris base 27g
- Boric acid 13.8g
- 0.5M EDTA 10ml
上記をビーカーにとり、蒸留水を加えて撹拌溶解し、500mlに調整する。アガロースゲルでは10倍に希釈して使用する。
- RNA用の試薬に関して
蒸留水などのRNaseを除去するためにはDiethyl Pyrocarbonate(DEPC)を0.1%加え、37℃で12時間以上撹拌する必要がある。その後、DEPCを除くためにオートクレーブを行う。DEPC臭が完全になくなるまで行う。DEPCはenzyme inhibitorでもあるので注意する。また、Tris bufferを作成する時にはDEPCは用いないようにする。試薬定量に用いる天秤は、RNaseの定量は行ってはならない。
しかし、実験室でRNaseを用いない、遠心機やピペットマンなどの器具を分けるなどの工夫でDEPCを用いなくても、RNAの実験は十分に可能である。一般に蒸留水やミリQ水、特級以上のグレードの試薬、新品のプラスチック器具にはRNaseはほとんどないと考えてもよい。手や唾などの分泌物にRNaseは含まれているために、操作中はしゃべらないようにし、安全キャビネットを利用したり、必ず手袋を着用するなどの注意を守ると良い。
- その他
SDSやbacteriaの培地を作成する時は微粒子が気道にはいる可能性があるので、ドラフトなどを利用すると良い。Ethidium bromideやアクリルアミドなどは毒性が強いので、必ず手袋を着用し、扱いに注意すること。0.5M EDTAは、10N NaOHを加えていってpHが8.0にならないと溶解しない。5M NaClは飽和に近いのでミリQ水(蒸留水)を多めに入れ溶解する。
C. 廃棄物の処理に関して
実験で利用したプラスチック用具などには、有害な試薬が付着することが多いので一般の廃棄物とは区別する。エチジウムブロミドは毒性が強いので、必ず回収し処理を行うこと。組換え体を直接扱ったものは、必ずオートクレーブ等を行い、組換えDNA実験のガイドラインにしたがって処理する。
D. ピペット、ピペットマンなどの使い方
ピペットはかならず、ピペッターエイドなどを使用し、決して口では吸わないこと。
ピペットマンは、正確に扱うこと。よく、ピペットマン内に溶液等を吸い込むことがあるので注意する。また、ピペットマンが汚染された時は、分解掃除を試みる。
 |
| ①:0.1-2.0μl |
| ②:2.0-20μl |
| ③:20-200μl |
| ④:200-1000μl |
<扱い方>



ピペットマンの分量が正確かどうかは、水を吸い上げ、微量天秤でその水の量をはかることにより推定できる。遺伝子操作のほとんどの過程でピペットマンを使うことになるので、十分にその操作に慣れることが重要である。
E. 酵素の扱い方
酵素は保存の温度管理が非常に重要である。多くの酵素はグリセロールを加えてあり、-20から-40℃では凍らない。-80℃は凍ることがあるので好ましくない。保存冷蔵庫は家庭用の冷凍庫など自動霜取り装置のついているものは好ましくない。酵素を使用する時には、必ず氷を用意し、冷凍庫から出すとすぐに氷の上に置くこと。酵素のチューブを持つ時には、できるだけ上の方を持ち、酵素の入っている部位にはさわらないようにする。
F. DNA・RNAの定量
DNAやRNAの定量にはいろいろな方法があるが、OD260を測定するのが一般的で簡便な方法である。DNAの場合OD260=1の溶液は50μg/mlの濃度である、またRNAではOD260=1の溶液は40μg/mlの濃度である。この値を基にして計算する。この際に、OD260/OD280をとることにより、DNAやRNAの純度が推定できる。純粋なDNAの場合はOD260/OD280=1.8、RNAは2.0である。蛋白成分などの不純物が混入していると、この比は下がってくる。
G. 電気泳動
PCR産物やプラスミドなどの確認、サザーンブロット、ノザーンブロット、シークエンスなどほとんどの遺伝子操作に電気泳動は必要となってくる。電気泳動は、アガロースゲルかポリアクリルアミドゲルを利用することがほとんどである。一般的には、長いDNA(500bp以上)はアガロースゲル、短いDNAはポリアクリルアミドが用いられることが多い。アガロースゲルは、特殊なアガロースを用いることにより、2-4%程度のゲルで100bp程度までの解析も可能である。RNAの電気泳動はホルマリンなどの変性剤が必要である。シークエンスゲルでは尿素を加えた変性ポリアクリルアミドゲルを利用することにより、一本鎖のDNAを1bpの長さの差まで解析することができる。