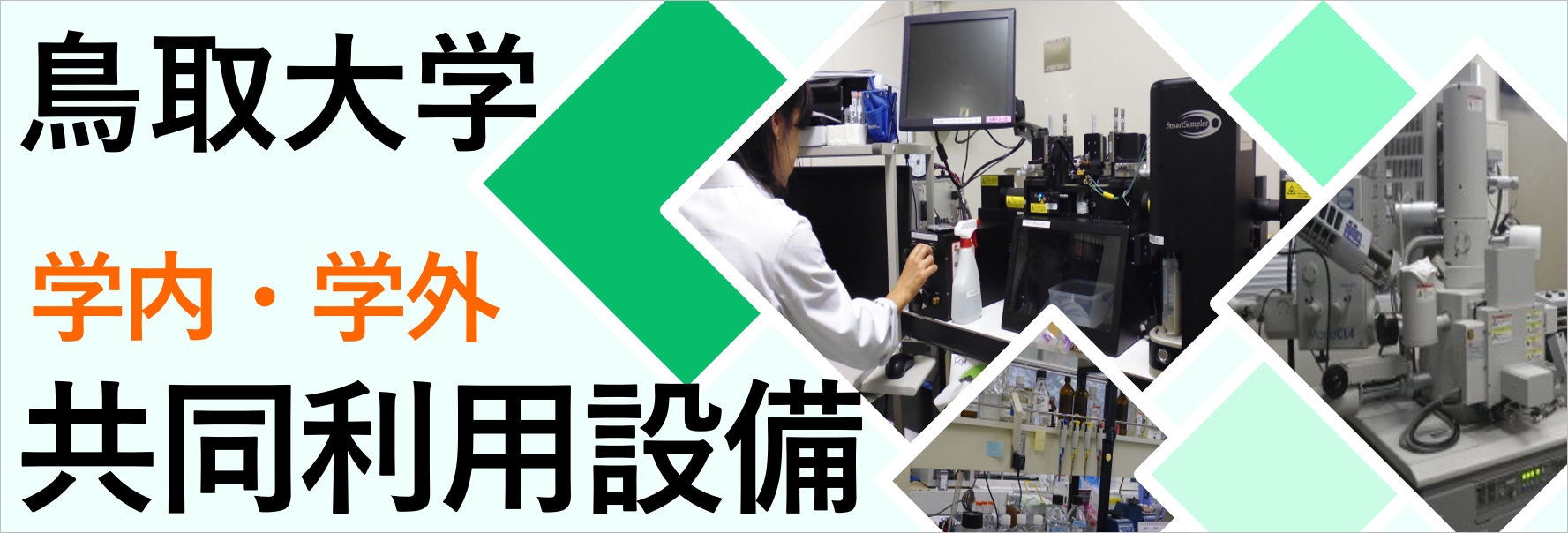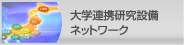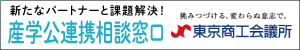- ホーム
- 研究基盤センター
- 学内の方向け
- 各種マニュアル(技術・情報提供)
- 遺伝子応用技術コース(FISH)
遺伝子応用技術コース(FISH)
FISH(fluorescence in situ hybridization)法とはクローン化されたcDNAまたはゲノムDNAをプローブとしてスライドグラスの染色体標本に直接ハイブリダイズさせ、目的のDNA配列の存在位置を直接マッピングできる方法である。これにより細胞遺伝学的地図の作製が可能となる。従来はラジオアイソトープ標識したDNAをオートラジオグラフィーにより検出する方法がとられていたが、1986年、化学標識したDNAプローブを蛍光染色し、シグナルを顕微鏡下で観察するFISH法が開発された。
目次
Ⅰ. プローブDNAの調製
今回、プローブDNAとしてはメジャーサテライトDNA、テロメアDNA、p9を用いる。
- セントロメアを検出するプローブ
- テロメアを検出するプローブ
- コスミドプローブ
- LB寒天培地
- Rapid solusion 1
- Rapid solusion 2
- Rapid solusion 3
- グリセロールストックから白金耳でLB寒天培地に塗抹する。
- 37℃にてインキュベートし出てきたコロニーを滅菌爪楊枝でアシストチューブ2mlのLB培地に拾う。
- 37℃にて一晩浸透培養し培養液1mlをエッペンドルフチューブに取る。
- 12000rpm、5min、4℃にて遠心する。
- 上清をデカントで捨て、氷冷したRapid solusion 1を100μl加えVortexする。
- Rapid solusion 2を200μl加え、ゆっくりと回転混和し、溶菌する。
- 5分間氷上に置く。
- 氷冷したRapid solusion 3を150μl加えゆるやかに混和する。
- 5分間氷上に置く。
- 12000rpm、5min、4℃にて遠心する。
- 上清(450μl)を新しいチューブに取りフェノールクロロホルム溶液を等量加えVortexする。
- 5分間置いた後、12000rpm、2min、4℃にて遠心する。
- 上清(450μl)を新しいチューブに取り900μlのエタノールを加えVortexし、2分間、室温にて置く。
- 12000rpm、5min、4℃にて遠心する。
- 上清を捨て70%エタノールを加え12000rpm、5min、4℃にて遠心する。
- 上清を捨て30μlのTEに溶く。
- 適当な制限酵素で3時間、37℃で消化させコスミドから切り出したDNAのサイズを電気泳動にて確認する。
- 目的の断片が確認できたら、RNaseを加え37℃で30分間インキュベートする。
- その後フェノールクロロホルム処理、エタノール沈殿し、TEに溶解し、OD濃度測定する。また、RNAが取り除かれているかどうか電気泳動にて確認する。
ビオチンまたはジゴキシゲニン標識済みの染色体特異的なαサテライトプローブが市販されている。ここではマウスセントロメアの反復配列であるメジャーサテライトDNAのPCRを用いて増幅する方法を紹介する。
プライマー:
5′ TACACACTTTAGGACGTG 3′
5′ CACGTCCTAAAGTGTGTA 3′
PCRの組成(primer 各1μM、dNTPs 各200μM、鋳型DNA(マウスゲノムDNA)0.1~10ng(種による)、1×添付バッファー、Taq polymerase 2Units)
| マウスゲノムDNA | Xμl |
| 滅菌蒸留水 | Yμl |
| 10×バッファー | 10μl |
| 2mM dNTPs | 10μl |
| primer 1(100μmol/ml) | 1μl |
| primer 2(100μmol/ml) | 1μl |
| Taq polymerase | 0.4μl |
| 計 | 100μl |
| サーマルサイクラーの条件: | ||
| 95℃ | 10min | |
| 94℃ | 3min | x 1 |
| 55℃ | 1.5min | |
| 55-73℃ | 2min | |
| 73℃ | 1min | |
| 95℃ | 10min | |
| 94℃ | 0.5min | x 23 |
| 55℃ | 1.5min | |
| 55-73℃ | 2min | |
| 73℃ | 1min | |
| 95℃ | 10min | |
| 94℃ | 0.5min | x 1 |
| 55℃ | 1.5min | |
| 55-73℃ | 2min | |
| 73℃ | 5min | |
PCR産物の5μlをミニゲルで電気泳動し、増幅の確認を行う。
(Agarose Sを用いて1.5% ゲルを作成し電気泳動を行う。プロダクトはラダーとなる。スメアーになるようなら鋳型DNAを減らすかサイクル数を減らす。)
残りのPCR産物はエタノール沈殿し保存する。使う時には10~50μlのTE溶液に溶解する。
染色体特異的なテロメアを検出プローブが市販されている。また、テロメア領域をPCRで増幅させプローブとして用いることも可能である。ここではPCR法を用いたテロメア配列増幅法を紹介する。鋳型DNAを必要としない。
プライマー:5′(TTAGGG)53′ と 5′(CCCTAA)53′
| サーマルサイクラーの条件 | ||
| 94℃ | 60 sec | x 10 |
| 55℃ | 30 sec | |
| 72℃ | 60 sec | |
| 94℃ | 60 sec | x 30 |
| 60℃ | 30 sec | |
| 72℃ | 90 sec | |
| 72℃ | 5 min | |
PCRの組成(primer 各1μM、dNTPs 各200μM、鋳型DNA(マウスゲノムDNA)0.1~10ng(種による)、1×添付バッファー、Taq polymerase 2Units)
| 滅菌蒸留水 | 77.6μl |
| 10×バッファー | 10μl |
| 2mM dNTPs | 10μl |
| primer 1(20μmol/ml) | 1μl |
| primer 2(20μmol/ml) | 1μl |
| Taq polymerase | 0.4μl |
| 計 | 100μl |
PCR産物の5μlをミニゲルで電気泳動し、増幅の確認を行う。
(Agarose Sを用いて1.5% ゲルを作成し電気泳動を行う。プロダクトはラダーとなる。スメアーになるようなら鋳型DNAを減らすかサイクル数を減らす。)
残りのPCR産物はエタノール沈殿し保存する。使う時には10~50μlのTE溶液に溶解する。
染色体の特定の領域や遺伝子を検出するには、特異的DNAプローブを用いる。このプローブのサイズは、500bp以上あれば可能であるが、通常は40kb程度のコスミドを用いることが多い。
Mini prep法によるコスミドDNAの調製
試薬
| Bacto tryptone | 10g |
| Bacto Yeast extract | 5g |
| NaCl | 10g |
| Bacto agar | 15g |
ミリQ水を加えて1lにする。以上を加えオートクレーブしある程度冷ましてから培養ディッシュに流し込む
| Glucose | 0.9g |
| 0.1M Tris-HCl(pH8.0) | 25ml |
| 0.5MEDTA(pH8.0) | 2ml |
MQで100mlとする。30分間オートクレーブ処理し室温保存。
| 5N NaOH | 400μl |
| 10%SDS | 1ml |
| MQ | 8.6ml |
をアクリル製チューブにて混合する。室温にて2,3日保存可能。氷冷はしない。
5M 酢酸カリウムを 60ml、酢酸を11.5ml、MQ 28.5mlを混合する。4℃保存。
操作
Ⅱ. プローブDNAのビオチン標識
反復配列を含むコスミドプローブなどを用いる場合、標識していないヒト由来ゲノムDNAやヒトCot-1 DNAを標識されたプローブと混合し、反復配列との雑種形成を行い反復配列を介するハイブリダイゼーションを抑え特異的なシグナルの検出を行う。プローブはタンパク質などが付着する標的DNAにハイブリさせるのでその大きさに由来する立体障害を考慮し、サイズを適当な大きさに調整する必要がある。また、プローブフラグメントは大きすぎると、その中の反復配列がヒトDNAとハイブリしてしまい、高い非特異的吸着の原因となる。逆に100塩基よりも小さい場合、標識効率が低下しシグナルの検出が困難となる。ハイブリダイズするのに十分な長さを持ち、なおかつ反復配列を同時に多数含まないプローブサイズ(250塩基を中心に100-500塩基に分布)を選択することが重要である。
コスミドやプラスミドなどのプローブではインサートの切り出しは行わない方がよい。濃度はベクターを含みプラスミド、およびコスミドでは500ng/μl、ファージクローンでは1μg/μl程度のものが適当である。DNA量は染色体標本1枚あたりプラスミド、およびコスミドでは200~300ng、ファージクローンでは500ng程度が適当である。標識はニックトランスレーションキット(Boehringer)を用いて行う。
フラグメントサイズに影響を与える因子としてDNase濃度、標識塩基の種類、反応時間が関係する。ビオチン化-16-dUTPとビオチン化-11-dUTPでわずかに異なり、ジゴキシゲニン化-11-dUTPでは大きく異なる。ジゴキシゲニン化-11-dUTPの方がビオチン化dUTPよりもDNAに取り込まれる速度が遅く、同量のDNase存在下ではジゴキシゲニン標識プローブの方が小さな標識フラグメントとなる。また、反応時間は長いほど反応液中のDNaseの作用時間が長くなりより小さな標識フラグメントとなる。今回はビオチン化-16-dUTPによるDNAの標識を行う。
試薬
- ニックトランスレーションキット(Boehringer)
- ホルムアミド(Boehringer 特級)
- 4M 酢酸アンモニウム
- 酢酸アンモニウム(Wako 特級)30.8gをMQに溶解し100mlとし、30分間のオートクレーブ処理する。室温保存。
- サケ精子DNA(10μg/μl)(Sigma)
- エタノール
- ヒトCot-1 DNA
操作
- 標識
- 下記の試薬をエッペンドルフチューブに入れよく混和する。
- 15℃のウォーターバスに入れ1.5時間反応させる。
- ヒートブロックで65℃、10分間処理し反応を停止させる。
- 室温に5分間程度放置し、冷却する。
- エタノール沈殿
- 下記の試薬を加えよく混和する。
- -80℃で30分間、または-20℃で15時間程度静置する。
- 15,000rpm、4℃で15分間室温で遠心する。
- 上清を完全に取り除く。
- 20μl (使用するプローブDNAが1種類の場合)のホルムアミド(Boehringer 特級)を加える。この状態で4℃にて2-3ヶ月保存可能である。)
- プローブDNAの変性
- ホルムアミド溶解のプローブを75℃ヒートブロックで10分間加熱処理し、DNAの変性を行う。(プローブDNAのヒト反復配列へのハイブリを抑制する時はこの段階でヒトCot-1 DNAを混合し同時に変性を行う。)
- 氷水中で5分間冷却する。
- 染色体標本の処理
- 保存しておいた染色体標本を65℃インキュベーターに入れ3時間放置する。
- 室温に戻し、ダイヤモンドペンシルによりハイブリダイゼーション領域をマークする。
| (染色体標本2サンプル分) | |
| dUTP(0.4mM) | 2μl |
| dGTP(0.4mM) | 2μl |
| dCTP(0.4mM) | 2μl |
| 10×NTB | 2μl |
| プローブDNA(0.5-1.0μg) | Xμl |
| 滅菌蒸留水 | (9.0-X)μl |
| ビオチン-16-dUTP(1mM)(Boehringer) | 1μl |
| 酵素液(DNaseI,DNApolI) | 2μl |
| 計 | 20μl |
| 反応終了液 | 20μl |
| 4M 酢酸アンモニウム | 2.5μl |
| サケ精子DNA(10μg/μl)(Sigma) | 2μl |
| エタノール | 56μl |
* 複数のプローブDNAを用いるときは溶解するホルムアミドの量に注意する。プローブDNA溶液とハイブリダイゼーション溶液が1:1となるように全量20μlを染色体標本に播種する事が重要である。
染色体ハードニング
Ⅲ. 染色体標本の作製
材料
ヒト正常繊維芽細胞、マウス初代胚性繊維細胞、マウスA9細胞
試薬
- 10%CS/DMEM
- トリプシン液
- コルセミド溶液
- 低張液(0.075M KCl)
- カルノア液(固定液)
ペニシリンG(100U/ml)およびストレプトマイシン(100μg/ml)含有のダルベッコ改変イーグル培地(DMEM: Dulbecco’s modified eagle’s medium)にウシ血清(CS : bovine calf serum)を10%添加する。
Tripsin(1:250, Difco)を2g、PBS(-)を19.2g、EDTAを0.8g、ミリQ水に溶解しミリポアフィルター(0.22μm)で濾過した後、50mlチューブに40mlずつ分注し-20℃にて保存する。
ミリQ水で10μg/mlを作製し4℃にて保存する。最終濃度が0.05μg/mlとなるよう培養液に加える。
KCl(特級)5.6gを1lのMQに溶解する。室温保存
メタノール(特級):酢酸(特級)(3:1,v/v)、使用直前に作製する。メタノールの変わりにエタノールを用いても良い。
操作
- ヒト繊維芽細胞の培養
- コルセミド処理
- 低張処理および固定
- トリプシン処理により細胞を培養ディッシュから収穫する。
- 回収した細胞を1,200rpで5分間遠心する。
- 上清をアスピレートする。
- 低張液(0.075M KCl)を5ml加えピペッティングし、15分間、室温にて静置する。
- カルノア液を5ml重層する。
- 混和後、1,200rpmで5分間遠心する。
- 上清を捨てカルノア液を15ml加え1,200rpmで5分間遠心する。
- 上清が透明になるまで、遠心、上清除去の操作を繰り返す。
- 固定液を加え適当な細胞密度にする。
- スライドグラスへの展開
- スライドグラス(白縁磨フロスト 井内)を50%エタノール溶液に浸す。
- カルノア固定した細胞液をパスツールピペットで1~2滴スライド上に落とす。
- ガスバーナーで熱し乾燥させる。
- 位相差顕微鏡で観察し、細胞密度、染色体の展開具合、染色体の長短などを確認する。
- 作製後室温に1週間程度置き染色体をスライドグラスに固着させ、-80℃にて保存する。
10%CS/ DMEM溶液にて細胞を培養する。(5%CO2,37℃) 染色体標本作製の前日には培地交換を行う。
コルセミド溶液(10μg/ml)を25μl添加し、1時間培養する。使用濃度および処理時間は細胞の種類や増殖の程度により変える。
(火炎固定法)
固定液を直接スライドに滴下し、蒸気により乾燥させる展開方法もある。使用する細胞により展開方法や条件を変化させる。
Ⅳ. ハイブリダイゼーションと検出
試薬
- 20×SSC
- 50%硫酸デキストラン
- 1%BSA/4×SSC
- 抗退色封入剤
NaCl 175.3g、とTrisodium Citrate 88.2gをミリQ水で溶解し1lとし、1N NaOHでpH7.0にする。30分間のオートクレーブ処理する。10×SSC、4×SSC、2×SSC、1×SSCは、20×SSCをオートクレーブ処理したミリQ水により希釈し使用する。
硫酸デキストラン(Pharmacia)50gを50mlのMQにスターラーで撹拌しながら溶解する。30分間のオートクレーブ処理し、分注し-20℃にて保存する。硫酸デキストランは粘性が高いので先端を切断したチップを使用する。
4×SSC 50mlに 0.5g のウシ血清アルブミン(albmin bovine, Sigma)を溶解しミリポアフィルター(0.22μm)で濾過した後、エッペンドルフチューブに500μlずつ分注し-20℃にて保存する。
PBS(-) 10ml にDABCO(1.4-diazabicyclo[2.2.2]octane, Sigma)を 1.25g 加えマグネットスターラーでよく撹拌して溶解する。グリセリン 90ml を加えよく混和し、さらに濃塩酸で pH8.7-8.8 に調整する。グリセリンは無蛍光のものでなくても良い。
- 染色体DNAの変性
- 70℃のホルムアミド(石津製薬 特級)/2×SSC溶液を満たしたコップリンジャーの中に染色体標本を2分間浸し、熱変性する。
- ただちに -20℃、70% エタノールに入れ 5分間静置する。
- 100% エタノールに5分間浸して脱水し、風乾する。
- ハイブリダイゼーション
- 以下のようにハイブリダイゼーション溶液を作成する。
- 変性済みプローブDNA溶液と等量づつ混合する。
- 混合液20μlを染色体標本に播種し、気泡が残らないようにパラフィルムをかぶせる。
- 湿気(2×SSC)を含んだ密閉箱(タッパー)に水平に静置する。
- 3℃で一晩(16-18時間)ハイブリダイズする。
- ハイブリダイゼーション後の洗浄
- パラフィルムを取り除く。
- 37℃のホルムアミド/2×SSC溶液で15分間静置し、洗浄する。
- 2×SSCで15分間静置し、洗浄する。
- 1×SSCで15分間静置し、洗浄する。
- 4×SSC中で保存する。
- FITCアビジン処理
- 1%BSA/ 4×SSC溶液100μlにFITC(fluorescein isothiocyanate)-アビジン( Boehringer)(2.5mg/ml)を1μl加え混合する。
- 4×SSCから染色体標本を取り出しFITCアビジン溶液を播種する。
- 気泡が残らないようにパラフィルムをかぶせる。
- 湿気を含んだ密閉箱に水平に静置する。
- 37℃で45分間反応させる。
- パラフィルムを取り除き、4×SSCに移し5分間洗浄する。
- 0.05%Triton X(Sigma)/4×SSCに移し5分間洗浄する。
- 4×SSCに移し5分間洗浄する。
- ビオチン化抗アビジン処理
- 1%BSA/ 4×SSC/溶液100μlにビオチン化抗アビジン(Vector)を1μl加え混合する。
- 4×SSCから染色体標本を取り出しビオチン化抗アビジン溶液を播種する。
- 気泡が残らないようにパラフィルムをかぶせる。
- 湿気を含んだ密閉箱に水平に静置する。
- 37℃で45分間反応させる。
- FITCアビジン処理の6-8の操作を行い洗浄する。
- 再FITCアビジン処理
- FITCアビジン処理の1-5操作を行う。
- FITCアビジン処理の6-8の操作を行い洗浄する。
- 2×SSCに移し室温で5分間静置する。
- DABCO溶液1mlにPI(propidium iodide, Sigma)(0.5~1μg/μl)を0.5μlもしくは DAPI(4′-6-diamidi no-2-phenylondole, Sigma)(100μg/ml)を2μl加え対比染色する。
- カバーグラスで封入する。
- マニキュアラッカーでシールした後、遮光し染色する。
熱変性処理の時間は標本の状態(作製時からの経過時間など)により適宜変化させる。
| 10×SSC | 50μl |
| ウシ血清アルブミン(BSA) | 25μl |
| 50%硫酸デキストラン | 50μl |
Ⅴ. 観察
特殊フィルター備え付きの蛍光顕微鏡にて観察する。フィルターはニコン社の場合PI(赤色)とFITC(黄緑色)の検出にはB-2A(励起フィルター450-490nm、吸収フィルター520nm)、FITC(黄緑色)のみの検出にはB-2E(励起フィルター450-490nm、吸収フィルター520-560nm)を用いる。また、DAPI染色はUVフィルターにより検出する。100 核板以上を観察し、染色分体に対称的なシグナル(ダブレット)を検出し、同じ染色体上の同じ位置にどのくらい観察できるかによりシグナルの位置を決定する。またレーザー顕微鏡を利用することもできる。
Ⅵ. FISHを用いたDNA複製時期の判定
細胞周期の間期の細胞核に対してFISHを行った場合、ある特定のDNAの核内における蛍光シグナルは二倍体細胞では複製前には2個のシングルドット、複製後には2個のダブルドットとして検出される。したがって計数した核の総数に対するどちらかのパターンの割合を算出することにより遺伝子の相対的な複製の時期を比較することができる。培養時にBrdU(ブロモデオキシウリジン)を取り込ませ、Rhodamin標識抗BrdU抗体でS期にある細胞のみを選択し、シグナルを計数することでDNA複製時期の判定が可能である。以下にFISH法と同時に行えるBrdU抗体法を示す。
試薬
- BrdU(5-bromodeoxyuridine)ストック溶液
BrdUを3mgと5N NaOHを20μl、MQ10mlに溶解し、0.22μmのフィルターに通し10-3Mとする。遮光し4℃にて保存。
操作
- 染色体標本の作製
- 抗体によるBrdUの蛍光標識
- ハイブリダイゼーション後の洗浄の後、FITCアビジン処理と同時に1%BSA/ 4×SSC溶液100μlにマウスIgG標識抗BrdU抗体(Amasham)を8μl加え混合する。
- 気泡が残らないようにパラフィルムをかぶせ、湿気を含んだ密閉箱に水平に静置する。
- 37℃で45分間反応させ、パラフィルムを取り除き、4×SSCに移し5分間洗浄する。
- 0.05%Triton X(Sigma)/4×SSCに移し5分間洗浄する。
- 4×SSCに移し5分間洗浄する。
- ビオチン化抗アビジン処理と同時に1%BSA/ 4×SSC/溶液100μlにTexas Red標識抗マウスIgG抗体(Amasham)を8μl加え混合する。
- 4×SSCから染色体標本を取り出し播種し、気泡が残らないようにパラフィルムをかぶせる。
- 湿気を含んだ密閉箱に水平に静置し、37℃で45分間反応させる。
- 以後、p16の5)ビオチン化抗アビジン処理、6以降に同じ。ただし対比染色はDAPIを用いる。
- 検出および観察
細胞培養の段階でBrdUを10-5Mの割合で加え、1時間インキュベートし、BrdUを細胞核に取り込ませる。以降は常法により作製する。
UVフィルターによりDAPIによる全核の染色を観察し、TXRDフィルターでBrdUが取り込まれた核を観察し、S期核を選択する。