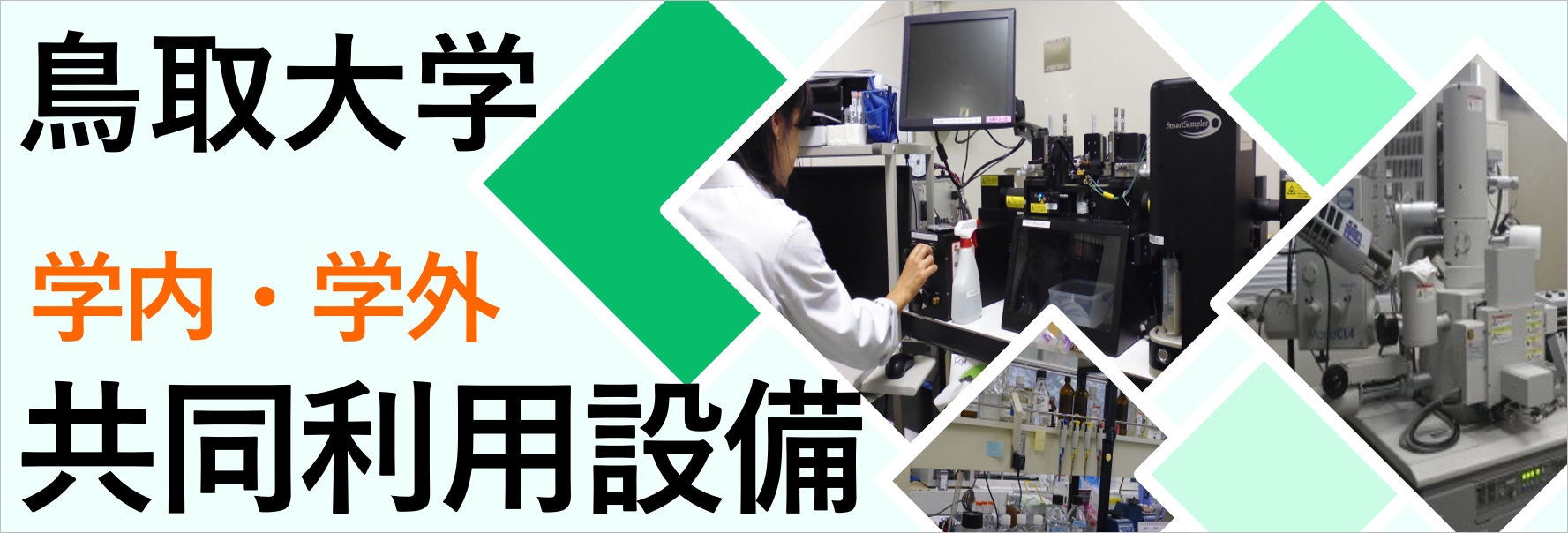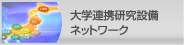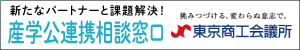鳥取大学「未来を拓く流儀」5周年記念miniシンポジウムを開催しました
1月23日、鳥取大学「未来を拓く流儀」5周年記念miniシンポジウムを開催しました。新井鷗子先生(横浜みなとみらいホール館長/東京大学客員教授/東京藝術大学客員教授)、田邑元一先生(ヤマハ株式会社研究開発統括部/東京藝術大学客員教授)を鳥取大学にお迎えし、「異なる社会資源をつなぐツールとは?」と題して基調報告・パネルディスカッション・「だれでもピアノ®️」(電子ピアノ版)の体験会を実施しました。当日はコミュニティ・デザインラボ(CDL・対面会場)、広報センター(パブリックビューイング会場)、オンライン会場に学生・教職員・一般参加者 約100名が集い、盛況となりました。
一本の指でメロディを奏でると美しい伴奏が人に寄り添うようについてきてくれる「だれでもピアノ」(東京藝術大学とヤマハ株式会社の共同研究開発)。新井先生・田邑先生による基調報告とパネルディスカッションでは、その着想の背景や技術開発の経緯、福祉・医療・教育など異なる社会資源をつなぐツールとしての可能性について、大学や企業・社会それぞれの目線から活発な議論を繰り広げました。続いて、新井先生の解説のもと、会場に設置した「だれでもピアノ」(電子ピアノ版)で「ファシリテーター養成講座」を体験しました。全体で90分という短い時間のminiシンポジウムでしたが、「だれでもピアノ」を囲んで地域や年齢を超えた人のつながりを創出する豊かな時間を共有しました。
コロナ禍でも研究開発の灯を絶やさずネットワークの拡大を続けてきた鳥取大学「未来を拓く流儀」(研究セミナー)は、この5年間で延べ1,100名を超える方々にご参加・ご視聴いただきました。応援下さったすべての皆さまに心よりお礼申し上げます。


河田康志・研究担当理事の冒頭挨拶

新井鷗子先生の基調報告

田邑元一先生の基調報告

保坂理和子 特命准教授(URA)の進行

メイン会場での体験会の様子

パブリックビューイング会場